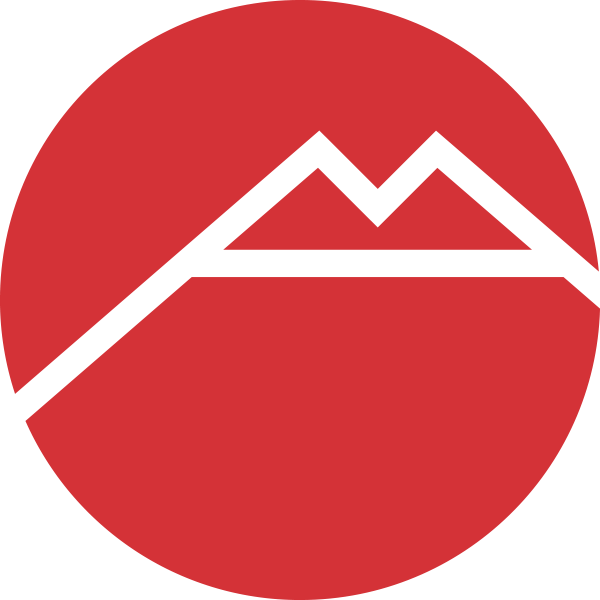世界を魅了するホスピタリティに満ちたタイの観光戦略/藤村喜章(タイ国政府観光庁 東京事務所 マーケティング・マネージャー)インタビュー

歴史的な王宮や寺院で知られる首都バンコク、世界遺産の古都アユタヤなどの観光名所に加え、ゴルフなどのスポーツや、象とのふれあい、タイ古式マッサージなど、多彩なアクティビティが楽しめる国、タイ。観光についての方針や戦略を観光・スポーツ省が定め、その傘下のタイ国政府観光庁が具体的な施策を進めるなど、国を挙げて観光戦略に力を入れていることで知られている。観光・旅行産業がGDPの約20%を占め、アジアの中でも突出しているタイは、どのような戦略によって世界中の人々を魅了し続けているのか。タイ国政府観光庁 東京事務所のマーケティング・マネージャー、藤村喜章氏に聞いた。
By AAJ Editorial Teamターゲット国ごとに設計した細かな戦略が タイの観光を押し上げた

ーータイ国政府観光庁(以下TAT)では、2025年の外国人訪問者数が4,800万人に達するとの見通しと発表しました。これは2024年の3,940万人を大きく上回り、コロナ前の水準にまで回復を見せています。また、日本人の訪問者数も2024年に100万人を超えたと聞いています。こうした成果は、どのような戦略によってなされたのでしょうか。
タイでは、各国に対して細かくセグメンテーションをした観光戦略を立てています。たとえば、日本に対しては、富裕層の親を持つ子どもや孫をターゲットにした「親リッチ」、韓国はゴルフ、インドはブライダル、北欧のスカンジナビアは老後のロングステイなど、その国に応じた観光戦略があります。各国に設置しているTATの拠点が、その国のニーズは何か、タイに何を求めているのかを詳細に把握しながらきめ細かくテーマ設定をしているのです。
他の国々と同様、コロナ禍でタイの観光産業も打撃を受けたことは確かですが、その最中でもさまざまな対策をとっていました。たとえば、主要な観光地の一つプーケット島では、コロナのワクチン接種済みの外国人観光客を隔離期間なしで受け入れる「プーケット・サンドボックス政策」を実施。あるいは、ホテルでの隔離検疫の代わりにゴルフ場でラウンドをしながら2週間の隔離検疫が行える「ゴルフ隔離」など、外国人観光客をつなぎ止めるような措置をとっていました。

ビーチリゾートとして知られるプーケット島では、コロナ禍に隔離検疫が免除される「プーケット・サンドボックス」を実施し、外国人観光客の維持に成功した。写真提供:タイ国政府観光庁
ーー現在、タイの外国人観光客のランキングでは、マレーシアが1位で、中国、インド、ロシア、韓国と続き、日本は5〜6位だそうですね。
円安や物価高、航空運賃の高騰なども影響して、2025年1月から9月までの日本からの観光客者は約80万人。日本へ観光に行くタイ人が81万人なので、出ていく人と訪れる人がほぼ同数という意味ではバランスがとれています。タイでは「タイランドプリヴィレッジカード」(タイランドエリートカード)という制度があり、65万バーツ(約300万円)以上を支払うと5年間のビザが付与され、専用のイミグレーションサービスなどが受けられます。日本人も約1,000人以上がこのカードを所持していますよ。
マレーシアは、近距離ということもあって国内旅行のような感覚で訪れる人が多く、観光客数は年間300万人以上に達します。欧米からの観光客の数自体は多くないものの、平均滞在日数が11日(日本人は7日)と長く、消費額も大きいため重要なマーケットといえます。さらに欧米からは、特定のオフィスを持たずに世界中を旅しながら仕事をする「デジタルノマド」の来訪が増えているのも近年の特徴です。
ーータイでは毎年度、政府として明確な観光戦略を打ち出しているとお聞きしました。
2024年10月から2025年9月まで、タイの観光キャンペーンとして「アメージング・タイランド・グランド・ツーリズム&スポーツ・イヤー」を打ち出しました。特にゴルフには力を入れていて、石川遼選手をタイ・ゴルフ観光親善大使に任命し、年間を通じてプレーができる気候であることも含めてタイでのゴルフの魅力をアピールしています。タイでは、プレーヤー1人につき1人のキャディが付くのが特徴です。カートの運転からクラブの管理、バンカーならしやボール探しなど、専属のキャディが親身になってサポートしてくれます。こうしたホスピタリティのあるサービスが、海外からの観光客に大きな癒しを与えているといえるでしょう。
2025年10月からは「Healing is the New Luxury 癒しこそ、新しいラグジュアリー」というテーマで観光キャンペーンを展開しています。これは、モノではなく体験することの価値を前面に打ち出し、自然、食、伝統的な工芸やお祭りなどに触れながら、心と体を癒す時間こそが最高のラグジュアリーである、という新たな提案です。
首都バンコクだけでなく 地方の魅力をいかに伝えるのかがカギ
ーー近年、日本国内では有名な観光地に観光客が集中することから起こるオーバーツーリズムが問題視されていますが、タイでも同様の問題は起きているのでしょうか。
もちろん首都であるバンコクに人は集中しますが、それ以外にも、映画『ザ・ビーチ』のロケ地になったピピ・レイ島に観光者が殺到したことから、2018年から2022年まで、自然環境保全のために一時閉鎖する事態になったことがあります。とはいえ、タイの面積は日本の1.4倍あり、そこに77県が点在しているので、人々が分散し、日本のような一極集中の問題はさほど起きていません。
地方観光の促進策として、Community Based Tourism(CBT)という取り組みもあります。たとえば、チョンブリー県バン・ラモン郡にあるタキアンティア・コミュニティでのココナッツを無駄なく使う取り組みや、チェンマイでのファイヤ―・マッサージなど、地方の人々の伝統や文化を守る活動を積極的に紹介しています。また、「持続可能な観光のための指定地域管理局(DASTA)」という組織もあり、豊かな地方文化を支えるしくみが整っている点も、一極集中の回避につながっているといえるでしょうね。

タイ北部のチェンマイの伝統的な温熱マッサージ「ヤムカン」。ファイヤー・マッサージとも呼ばれ、火で熱した足裏で行う独特の施術が外国人観光客にも人気だ。写真提供:タイ国政府観光庁
タイ東部チョンブリー県のタキアンティア・コミュニティでは、ココナッツの葉を使った飾り作りや地元の伝統的な料理作りを体験できる。写真提供:タイ国政府観光庁
ーー地方の豊かな資源に目を向けることで、さらにタイ観光の奥行が広がっていくわけですね。タイの今後の観光戦略はどのようなものになりそうでしょうか。
今後の展開としては、「3つのL」を重視しています。1つ目は「Leisure(レジャー)」で、タイの多様な観光資源をより活用してもらうこと。2つ目は「Live(生活)」で、タイでの生活体験の促進やデジタルノマドの滞在を促すこと。3つ目は「Link(連携)」で、ビジネスとの連携をはじめ、「ツーウェイ・ツーリズム」として、たとえばタイの東北と日本の東北をつなぐような地域間連携を進めることなどが挙げられます。こうした戦略を通して、タイの観光産業をさらに多面的に発展させていきたいと考えています。
いま、観光客の旅のスタイルも大きく変わってきています。タイを訪れる観光客の約85%が、団体旅行ではなく、個人で航空会社やホテルを手配するFIT( Foreign Independent Tour)です。旅行会社を通さず航空会社やホテルの予約を直接やりとりする人やOTA(Online Travel Agent=オンライン旅行代理店)の利用が増えているため、既存の旅行会社の存在意義が問われています。旅行会社は、刻々と変化する現地情報を的確にキャッチして発信する力や、顧客のニーズを掘り起こして適切な場所に送り届けることがより一層重要になります。バンコクにだけ着目するのではなく、地方にも目を向けていけば、まだまだ観光客に対してユニークな提案ができるのではないでしょうか。
タイの観光戦略から日本が学ぶべきなのは、ホスピタリティのあり方だと思います。日本にも「おもてなし」の文化はありますが、やや杓子定規というか、外国人観光客の望みに対して、「それはできません」「それはありません」という画一的な答えしかできないケースが多い。タイでは、「それはできないのですが、これならできます」といった他の選択肢を提案します。そうしたフレキシブルな対応が、観光客にホスピタリティを感じさせるのでしょう。その辺りを、日本もタイから学ぶ必要があるんじゃないかなと思いますね。
【プロフィール】
藤村喜章
タイ国政府観光庁東京事務所のマーケティング・マネージャー。中央大学卒業後、2年間企業に勤務し、南イリノイ州立大学大学院に留学。帰国後、旅行会社勤務を経て、1999年タイ国政府観光庁に入庁。総合旅行業務取扱管理者の資格を持つ。
https://www.thailandtravel.or.jp/
写真/坂本政十賜
文/さくらい伸