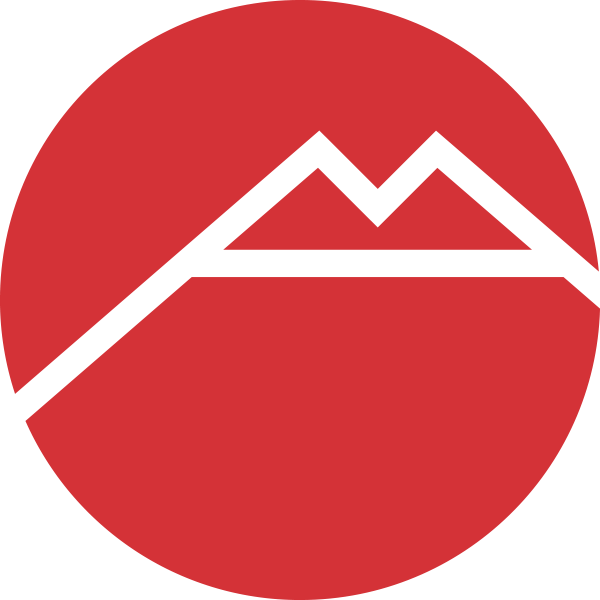Uncharted Tokyo 3| 母島のサステナブル・ファーム 観光と環境の共存を目指して

東京といえば、渋谷や浅草などのにぎやかな街を思い浮かべる人が多いかもしれない。けれど、都心から少し離れた多摩・島しょ地域には、まだ知られていない“もうひとつの東京”が広がっている。海や森、集落の暮らしの中で出会う体験は、ただの観光ではなく、心を動かす旅の入り口だ。環境に配慮しながら、好奇心と冒険心の赴くままに進む——それが、いま世界で注目される旅の新しいかたち。「Uncharted Tokyo(あなたの知らない東京)」へ、今こそ踏み出そう。
By AAJ Editorial Teamここがまだ東京都だなんて、にわかには信じがたい。けれど、私はいま、東京の本土から最も離れた小さな島の小さな農園で、人生でも屈指のマンゴーを頬張っている。あごを伝った果汁が地面にぽたりと落ち、周囲を見渡せば、温室にはトロピカルフルーツとカカオ。その向こうには、ジャングルのようにそびえるヤシの木々―――日本の首都・東京の喧騒や超近代的な街並みから、これほど遠くに感じられる場所があるなんて。
私が訪れたエコツーリズム施設「タエコニ農園」は、東京の南約1,000キロ、小笠原諸島の母島にある。ここで、ツアーガイドの小西稔紀さんと諸澤妙子さんは、地元農家の折田一夫さんらとともに、ツアーや体験を通じて、サステナブルな農の営みと自然保全を伝えている。

小笠原諸島母島にてタエコニ農園の運営とガイドツアーをする(左)小西稔紀さんと(右)諸澤妙子さん。
農園の案内をしてもらっていると「マンゴーは、普段のツアーには含まれていないんですけどね」と諸澤さんが笑う。「折田さん、機嫌がいいと配ってくれるんです」。「皮はそこに投げておいていいよ」と折田さん。「鳥が食べるから」。ちょうどその時、小さな野鳥が2羽、目の前を横切った。諸澤さんによれば、それはハハジマメグロで、国の天然記念物に指定されているという。「地球上でこの島にしかいない鳥なんです」と、その緑と黄色の小さな体を指さして、教えてくれた。

船路で辿り着く世界自然遺産の地で、ゆっくりと流れる時に身をゆだねる

小笠原諸島の母島には、約400名ほどの島民が暮らしている(2025年8月1日現在)
小笠原諸島は、訪日客の多くが知らない「東京の隠れた魅力」を体感させてくれる。固有の動植物が息づく森を抱くユネスコの世界自然遺産であり、ひっそりとした入り江と、信じられないほど澄み切った青い海が広がる。1年を通じてイルカやアオウミガメと海に潜ることができ、早春には波間で戯れるクジラを望むことも可能だ。
ただし、簡単には辿り着けない。その道のりが、この地をより特別で記憶に残る場所にしている。島々へ行く手段はただひとつ。東京・竹芝桟橋から父島へ向かう定期船に乗ることだ。所要は約24時間。忙しい現代人にとっては少々長い時間に感じられるかもしれないが、この航海自体が特別なものだ。出航してしばらくすると電波が途切れ、乗客たちはゆっくりと“休暇モード”へ。トビウオを追う海鳥をデッキシートで眺めたり、ラウンジで一杯やりながらくつろいだり。天候に恵まれれば、夜のスカイデッキからは日本でも屈指の星空が望め、早起きして眺める朝日も格別だ。父島に到着後、多くの人々がそのまま滞在してダイビングへ向かう一方、母島を目指す人は小さな連絡船に乗り換え、さらに南へ約2時間進む。

小笠原諸島はいくつもの島々で構成され、有人島は父島と母島の二つのみ。
この大きなハードルこそが、母島をオーバーツーリズムから守ってきた。
「小笠原の玄関口である父島行きの船は6日に1便、定員も限られています。さらに父島から母島へは2時間かけてさらに船に乗らなくてはいけない」と、諸澤さん。「だから、訪問客が押し寄せて困るという心配はありません。やってくる人は少なくとも3泊はすることになり、島のことをじっくり理解したうえで、島を好きになって帰ってくれます」。
母島まで足を運ぶ人のために、タエコニ農園では多彩なツアーや体験を用意している。固有種の森を歩いて絶景を巡るガイドハイクやトレッキング、車で島の自然と史跡を辿る観光ツアーなどに参加できるのだ。なかでも、諸澤さんのお気に入りは、6時間かけて歩く乳房山(ちぶさやま)へのトレッキング。「今日は、海からの湿った風で雲に隠れていますけど…」と、低く垂れ込める雲を指差す。「この山にいる固有のカタツムリが、世界自然遺産登録の決め手になったんです」。小さな生き物ひとつが、この島の価値を世界に示したと聞くと、道すがらの風景もより特別に感じられる。

母島固有のカタツムリ。小笠原の世界自然遺産登録時の評価にもつながった、貴重な島の固有種。
日帰りで滞在する人向けには、島唄のウクレレ体験や伝統工芸のワークショップのほか、母島の恵みを味わえるプログラムもある。例えば「島レモンジャムづくり」では、農園で栽培されているレモンを使用。一般的なレモンよりも香りが強く酸味が爽やかで、母島の家庭でも親しまれてきた在来の柑橘だ。もうひとつの人気体験「カカオニブづくり」では、近年母島で栽培が始まったカカオを使い、発酵・焙煎したカカオ豆を砕いて“ニブ”と呼ばれる小片に加工する。チョコレートの原料そのものを味わえる体験で、島ならではの新しい農業の試みを知ることができる。

タエコニ農園で採れたレモンを使ったジャムづくり
諸澤さんが「タエコニ農園の体験プログラムは、1時間半~2時間ほどなので、父島からの日帰りでも、午前10時頃に始めてお昼前には終わります。昼食や資料館見学、海遊びなどとも無理なく組み合わせられるんです」と教えてくれた。「午後の船に間に合わせるために慌ただしく終えるのではなく、母島らしい“ゆっくりした時間”を感じてもらえるはずです」。

課題を乗り越えながら一歩ずつ。危機から生まれた新しいチャレンジ

(左)地元農家の折田一夫さんと(右)タエコニ農園の諸澤妙子さん
タエコニ農園の着想は、2020年のコロナ禍に生まれた。世界中の多くの地域と同じく、小笠原でも4月から6月にかけて島が封鎖され、観光は一夜にして消えた。以前は、母島観光協会に勤めていた諸澤さん、ガイドをしていた小西さんも、突然まとまった時間を持て余すことに。
「そんな時に折田さんが『時間あるならスイカ作りを手伝わない?』って声をかけてくれて」と諸澤さん。「畑で土に触れて、美しい景色を眺める―あのストレスの多い時期に、とても癒やされたんです」。「土地とつながるこの感覚を、訪れる人にも体験してほしいと思いました。ただの観光にとどまらず、農を通して島を“学び、感じる”ことを」と言葉を続ける。
母島では、豊かな自然と亜熱帯の気候風土を利用しパッションフルーツ、マンゴー、島レモン、カカオなど、収益性の高い作物が栽培されており、母島ブランドとして重要な地域資源だ。また、農地やその周辺の自然環境は母島の観光資源であり、実際に農地を見学することは自然環境について学ぶきっかけとなる。ただ、それを実現するには問題があった。それらの土地は赤土がむき出しになっているため、観光客の靴底に赤土がつき、土壌中に潜む外来種の拡大を招いてしまう恐れがあったのだ。
そこで、タエコニ農園が実施するハイキングなどの体験では、島の宝を脅かしかねない外来種の拡散防止には細心の注意を払うように努めている。「山から山へ移動するときには、衣服についた植物の種や、靴裏についた動物の卵を持ち込まないように気をつけます」と、小西さん。「泥落としマットを使うなど、お客様にも同じように注意していただきます」。東京都のレンジャーも、島間移動の際には、船に乗る前に靴底を清掃するよう呼びかけているという。

(左)保護区域入り口で、訪問者に靴底の清掃方法を案内する小西さん。(右)靴裏用の清掃マットと酢スプレー。生態系への影響を抑える工夫だ。
そして、もうひとつの問題が、母島での観光コンテンツはトレッキングやダイビングなど、山・海のアクティビティが主体で、荒天時に対応できるアクティビティが皆無であることだった。しかも、荒天時のトレッキングでは、ルートがぬかるみ、ぬかるみを避けるためにルートの脇を歩けば、さらにルートが荒れてしまうという悪循環が生じる。
こうした外来種の拡散防止と、荒天時にも観光が成立する受け皿づくりに対応し、運用や体験設計の改善を重ねていくことも、タエコニ農園の役割のひとつとなっている。

タエとコニ、島の人々と出会いから始まる物語

キッチンや工房などが入るコンテナの前にて。
母島に根を下ろす前、都心部で、諸澤さん(タエさん)はバイオテクノロジーの研究職として、小西さん(コニさん)はシステムエンジニアとして働いていた。2013年の東京の厳しい冬をきっかけに「もっと暖かい場所で働こう」と考え、二人は南の島での仕事を探す。「あの時動かなければ、一生変われないと思ったんです」と、諸澤さんは語る。「求人を探して、母島観光協会の仕事を見つけました」。その後、旅行会社や行政との調整など、8年間にわたって観光の現場に携わった。
タエコニ農園の成功は、二人が13年をかけて築いた地域とのつながりに支えられている。なかでも、代々この島で暮らす折田さんの存在は大きい。「折田さんがいなければ、ここでやっていくことはできなかったと思います」と、諸澤さん。
二人の最初の出会いは、毎日出航する船を皆で見送る港でのこと。鯉のぼり(こいのぼり)だと思い込んだ折田さんに、諸澤さんが「これは“くじらのぼり”なんですよ。島のシンボルなんです」と訂正したのがきっかけだったという。そんなやり取りから親交が生まれ、やがて一緒に仕事をするようになった。
折田さんは諸澤さんに島での農業の方法を教え、いまではカカオの温室やシマレモンの畑、マンゴーの木にも案内してくれる。カカオへの取り組みは2011年に始まり、埼玉県の平塚製菓が国内でのカカオ栽培を模索する中で折田さんとタッグを組んで、母島で栽培されたカカオを100%使用したチョコレート「東京カカオ」を生産してきた。プロジェクトは今年終了し、今後は折田さんが温室と樹木を引き継ぎ、現在はタエコニ農園と共有。これが「農園見学&シマレモンジャムとカカオニブ作り体験」の土台になっている。

(左)母島で栽培されるカカオの実。中にはチョコレートの原料となる豆が詰まっている。
(右)発酵・焙煎したカカオ豆を砕いた「カカオニブ」。チョコレート作りの原点だ。
諸澤さんは、島内のほかのガイドとも連携し、限られた資源を最大化すべく努めている。「母島にはガイドが多くおりません。力を合わせて設備を共有すれば、個々の環境負荷を抑えながら、より多様な体験を提供できます」。
目指すのは、来訪者の快適さと環境配慮の両立だ。「母島には、来て、見て、帰るだけではなく、快適に過ごしつつも、“学び、味わい、感じる”場所であってほしい」と小西さん。

単なる観光ではなく、母島の自然を深く知る体験。動植物や地形を理解し、安全に導く知識と経験に支えられている。

母島の自然を守りながら、いつでもまるごと感じられる体験施設

雨天時にも体験できるタエコニ農園の施設は着々と完成に向かっている。
「これまでは急な高温や台風で、体験の中止や移動を余儀なくされることがありました」と、小西さん。「母島は天候の変化が早く、湿度も極端に高い。冬でも除湿機が手放せません。そこで新たに設けた屋内型の拠点では、季節や天候に左右されずに体験を提供できるようになりました」。
この日、カカオ農園での作業を終えると、諸澤さんと小西さんが改装済みのコンテナを見せてくれた。ジャングルの緑に映える軽やかな水色に塗られ、広い窓からは農園とその先の海が見渡せる。

このコンテナの中でさまざまな体験が可能になる。
20フィートサイズのコンテナが3基並ぶ。1基あたり約8.5畳と十分な広さで、出入り口の扉と大きな窓を備え、エアコンも設置されている。外にはウッドデッキを併設し、コンテナとは思えない使い勝手だ。内部には水回りを備えたキッチンが整い、ジャムづくりなどの調理体験に活用される。工具が充実した木工の工房になっているコンテナもあり、屋外で活動できない日でも、ものづくりを楽しめる拠点になっている。「雨や風だけでなく、今日のような暑さにも対応できる設計です。天候に関わらず、同じスペースを通年で活用できます。今後は島内の木材を使用してウクレレなどの楽器づくりも工房で提供したいですね」と語る小西さんの表情は明るい。

農園もハウス化されており雨天でも収穫体験などが可能だ
この施設の整備は、単に快適性を高めるだけではない。母島では、悪天候に対応できる観光コンテンツが乏しく、雨天の日に無理なトレッキングを行えば登山道の侵食が進んでしまう。そうした問題を防ぐために、悪天候時でも実施できる体験を提供し、さらにツアーごとの機材を運ぶ手間をなくす恒常的な拠点を備えている。この施設は、タエコニ農園が向き合ってきた課題に応える具体的な解決策でもある。
その後、母島を離れる船上で、私は岸壁で手を振る人々のそばに立つクジラのぼりと、地面に水で描かれた巨大なクジラに見送られた。隣で歓声を上げる家族連れの笑顔を見ながら、先ほど小西さんが話していた言葉を思い出す。

母島の港では、水で描かれたクジラとともに、多くの人々が見送りに集まってくれた。
「小さなお子さんのいるご家族にも来てほしいんです。子どもの頃の体験は本当に大切。『何十年ぶりにまた来ました』という方も多い。最初の記憶が、戻ってくる理由になるんです」
もっとこういう場所が必要なのかもしれない―。母島やタエコニ農園のように、私たちに“立ち止まること”を促すほど遠くにあり、わざわざ旅するに値する特別さがあり、そして次の世代が見つけて、訪れることができる、持続可能であり続ける場所が。

これまで数多くのツアーを企画してきた二人。ときには全盲の方を案内し、風や鳥の声、波音など“音と感覚で味わう自然”を体験してもらったこともある。

タエコニ農園
所在地:東京都小笠原村母島【地図】
アクセス:竹芝桟橋 →(おがさわら丸 約24時間)→ 父島 →(ははじま丸 約2時間)→ 母島
体験:農園見学・加工体験(詳細・料金はWEBサイト参照)
予約方法:公式サイトの予約フォームより
URL:https://poco.taekoni.com/
SNS:Instagram https://www.instagram.com/taekonifarm/


サステナブル・トラベラー/Andrew Lee(アンドリュー・リー)
ライターとして活動しながら、出版業界での豊富な経験を持つ。『The Japan Times』に10年間在籍し、2017年には紙面のリブランディングと再デザインを担当。日本各地の自然・文化・食に関する旅行記事を多数執筆。自ら現地を訪れ、体験に根ざした視点から地域の魅力を伝える。サステナブルツーリズムに関する取材経験と知見も豊富。
※本内容は、「公益財団法人 東京観光財団 環境配慮型旅行推進事業助成金」を活用して実施しています。
文/All About Japan編集部