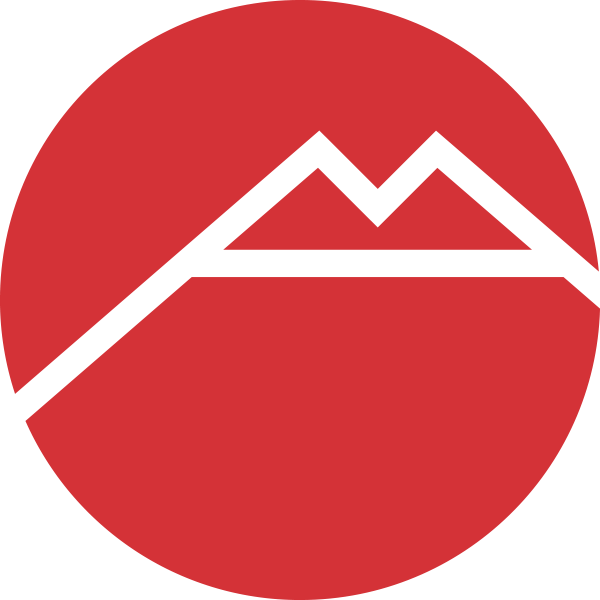Uncharted Tokyo 2| “森と水”が育む、東京・奥多摩のサステナブルステイ

東京といえば、渋谷や浅草などのにぎやかな街を思い浮かべる人が多いかもしれない。けれど、都心から少し離れた多摩・島しょ地域には、まだ知られていない“もうひとつの東京”が広がっている。海や森、集落の暮らしの中で出会う体験は、ただの観光ではなく、心を動かす旅の入り口だ。環境に配慮しながら、好奇心と冒険心の赴くままに進む——それが、いま世界で注目される旅の新しいかたち。「Uncharted Tokyo (あなたの知らない東京)」へ、今こそ踏み出そう。
By AAJ Editorial Team
水と森の町、奥多摩に滞在する旅へ

清流と四季折々の自然が織りなす風景が広がる奥多摩町
大都市・東京に広く水を供給し、都民の暮らしや産業を支える多摩川。その水をたたえる奥多摩湖を抱く奥多摩町は、東京都の最西端に位置し、町域の約94%を森林が占める“水と森の町”だ。
豊かな緑に加え、雲取山、鷹ノ巣山、大岳山などの峰々、そして多摩川とその支流が刻む渓谷の景観が四季を通じて人々を惹きつける。特に夏期は、登山やハイキング、渓流遊びを目当てに多くの旅行者でにぎわう。
JR青梅線の青梅駅から奥多摩駅までの区間は、多摩川上流域に位置する。都心と山間部を結ぶ生活・観光の動脈であるこの路線に沿って、渓谷や集落、里山の景観が連なっている。
奥多摩町の現在の人口はおよそ4,400人。近年は、観光客の増加とともに、観光ごみや駐車場渋滞、バーベキュー騒音などへの対策を進め、自然を守りながら無理なく観光客を受け入れる体制の整備に取り組んでいる。
大切なのは、環境に配慮しつつ1年を通して日帰りだけでなく、ゆっくり滞在してもらえるよう観光の設計を見直すこと。そうすれば、来訪は安定し、混雑は和らぎ、自然も守って活かせる。そこで生まれたのが、奥多摩の自然・文化・暮らしを体験として結びつけ、地域観光や移住促進、環境配慮型の滞在の拠点となる「Satologue(さとローグ)」だ。
Satologueは、JR青梅線・古里(こり)駅から徒歩約15分の場所にある。運営するのは、JR東日本と株式会社さとゆめの共同出資で設立された、沿線まるごと株式会社だ。地域の観光を持続可能なかたちへ再設計するにあたり、同社が推進する「沿線まるごとホテル」構想が礎となっている。無人駅舎をフロント、空き家や空き施設を客室、地域住民をキャストと見立て、鉄道沿線全体を一つのホテルとして機能させることで、地域の宿泊施設や飲食、自然・文化資源をつなぎ、「滞在して巡る」旅を促そうというのだ。
その中核拠点として位置づけられる「Satologue」には、2024年5月にレストランとサウナが先行オープンし、2025年5月に宿泊棟が加わり本格稼働を開始した。古民家を改修した宿泊棟やレストラン、倉庫をリノベーションし、奥多摩の間伐材を薪に用いたサウナなど、多様な施設が整えられている。さらに庭には、生きものが暮らせる小さな池や湿地を再現した、ビオトープ(生物の多様な生息空間)も整えられ、生態系を回復させる仕組みが取り入れられている。これにより、宿泊と食事、癒やしの体験が自然と一体となって楽しめる環境となっている。
さらに、森林セラピーや地元の食文化に基づいた料理、地域の人々のガイドによる奥多摩のアクティビティなど、地元の事業者とも連携し、多様なプログラムを展開。観光客がただ訪れるだけでなく、自然の恵みを感じ取り、地域社会とつながる仕組みを整えている。こうした取り組みにより「Satologue」は、奥多摩の豊かな自然と都市生活を結びつけるとともに、サステナブル・ツーリズムの地域モデルとしても注目されている。

2024年にオープンした「さとローグ」

秩父多摩甲斐国立公園の大自然の区域に存在する。

森と水とともに、奥多摩の記憶をよみがえらせる拠点

ラウンジの扉から表に出て階段を下りると緑豊かなウッドデッキやビオトープが広がっている。
さとローグは、ニジマス養殖を営んでいた大家さんの築約120年の旧邸宅を、構造と素材をできる限り残して再生した。かつての養魚場に並んでいた複数の生け簀に土を入れ整備された自家農園では、トマトやナス、青じそ、葉物野菜など、季節ごとの野菜やハーブが育てられている。来訪者は収穫体験を通じて自然の恵みを肌で感じることができ、収穫した食材は施設の料理にも使われ、滞在の楽しみをさらに広げている。

(左)シェフと一緒に自家農園にて野菜を収穫。(右)収穫された野菜は調理してもらい、レストランで味わうこともできる。
また、ビオトープの前には新たにウッドデッキが整備され、薪割りや焚き火などのアクティビティの実施や、腰を下ろしてくつろぐ場として活用されている。庭づくりも既存の樹木と地形を活かし、川と森の環境を守るという理念のもと、地域資源を使った体験空間として整えられた。
地域資源の活用は、建物だけにとどまらない。薪サウナ「風木水(FUKISUI)」では、奥多摩の間伐材を中心とした木材を薪として用いています。川の水を引いた水風呂や緑に囲まれた外気浴と合わせ、“場としての里山体験”を提供している。
敷地やその周辺には、奥多摩の歴史を体験できる仕掛けが随所に用意されている。コンセプトは、名称の「里(sato)」と「語り(logue)」にもある通り、「里とつむぐ、物語」。養魚場跡のビオトープや自社ファーム、わさび田、きのこの菌床栽培地などをスタッフや地域の方が案内するSatologueのフィールド散策は、奥多摩ならではの暮らしと自然の関わりを、見て触れて学べる貴重な機会だ。さらに、奥多摩のガイドツアーや集落巡りでは、良質な木材の供給地としての林業や、多摩川を使った筏流しの歴史についてもガイドから学ぶことができる。
こうして、「泊まる」「食べる」「巡る」という行為そのものが、単なる観光ではなく、地域の記憶をたどる旅となるのだ。“鉄道沿線を一体のホテルと見立てる”という考え方に沿って、記憶を体験として受け継ぐ仕組みがここに息づいている。

ラウンジスペース。本やフリードリンクなどもあり、静かな空間で自然を満喫。

倉庫を改築した薪サウナ。外には天然水の水風呂も用意されている。

沿線をまるごとホテルに 地域の暮らしに寄り添う“編集者”たち

以前は新幹線の車掌をしていたという、沿線まるごと株式会社の溝口謙太さん。
沿線まるごと株式会社の溝口謙太さんは、さとローグの立ち上げメンバーの一人。鉄道と地域をつなぐ「沿線まるごとホテル」の構想を現場で形にしてきた。
この「沿線まるごとホテル」では、JR東日本と地方創生事業のさとゆめが共同出資した沿線まるごと株式会社が、駅舎などの基盤と情報発信、ホテルの運営を支え、地域の事業者は飲食・体験に加え、農産物や工芸、郷土料理の提供を担う。住民は、ガイドと景観・自然の手入れを行い、祭りや伝承、昔話を通して地域の記憶を体験に織り込む。この三者の枠組みに沿って、さとローグでも日々の運営が行われている。
こうした連携を支えるために、溝口さんは戸別訪問や現地歩きを重ね、空き家の活用や受け入れのあり方を住民と話し合いながら整えてきた。
「できるだけ直接お会いして、私たちが目指す姿を丁寧にお伝えしました。地域の知恵や文化を活かし、みんなでおもてなしする取り組みだと。」(溝口さん)
その結果、無人駅では通常どおりSuicaなどのICカードで乗車できる一方で、地域の住民が案内役となり、昔ながらの切符にはさみを入れる代わりに、沿線まるごとホテル宿泊者に配るガイドブックにはさみを入れる場面も見られる。送迎の道中で動植物や歴史の案内を担う場面が増えたりするなど、日常のふるまいがそのまま接客につながっている。
住民だけでなく、各分野の専門家たちの存在も心強い。例えば、ランドスケープデザインを監修した造園家は「水や光、風の循環が外界とのつながりを生み、生態系を豊かにする」と語り、敷地内の庭や水辺をビオトープとして再生した。また、建築設計を担った建築家は、奥多摩の地形や川音を引き立てるよう“濃い味付けをしない”空間づくりを重視している。その他にも、森林や里山の管理に携わる専門家、地域の食を担う料理人や生産者、歴史や文化を伝える案内人、アウトドアガイドなど多彩な人材が加わり、プログラムや体験は少しずつ磨かれている。

シェフもまた一人の編集者として、地産食材を生かした料理を提供している。(写真:Daisuke Takashige)

川を感じ、森に癒される 五感でととのえる体験の数々

ラウンジ前にはデッキがあり、目の前には多摩川や愛宕山が見える。
Satologueで過ごす時間は、五感に訴える癒しに満ちている。敷地エリアの自家農園では、シェフと一緒に収穫した旬の野菜が調理されて、レストランでその日の夕食として供される。畑で摘んだハーブをお茶にするなど、暮らしの手仕事が自然とつながる。ビオトープやウッドデッキでくつろぎ、薪サウナでととのった後は川辺で外気浴。
また、地域と連携した体験プログラムも複数ある。そのひとつが、TOKYO WASABIの角井仁さん・竜也さん兄弟が実施する、わさび田ツアーだ。東京とは思えない大自然の山林を分け入り、真夏でもひんやりした清流が走る棚田状のわさび田へ向かう。採れたてのわさびをその場ですりおろして味わえるのは、忘れられない体験となるだろう。
奥多摩の自然と人々に惹かれて移住してきた角井さんたちは、放置されていたわさび田の存在を知り、地元農家やプロの指導のもとで再生を進めてきた。奥多摩の谷は狭く、農機が使えないため、すべて手作業で石を1つ1つ積み、清らかな水が流れる棚田状の畑をつくり上げたという。「農業を営んでいるというより、自然環境を手入れしている感覚に近いですね。笑」(弟/角井達也さん)
さとローグの運営は、環境への配慮を軸としている。国立公園のルールに従い、むやみに新築せず、築百年超の空き家は壊さずに骨組みを生かして再生し、養魚場の生け簀は農園とビオトープへと姿を変えた。
「外来種はできるだけ残さず、昔からの植物を戻すようにしています。敷地全体で“ミニ奥多摩の生態系”をつくっている、そんな感じです。畑の野菜は猿に食べられてしまうこともあるんですが、それも自然の一部だと受け止めています。」(溝口さん)
また、川沿いは、2019年の台風被害の教訓を踏まえて増水リスクを見込み、水を尊重した配置に。
「奥多摩は林業の盛んな土地なので、この地で取れた薪を使っています。そこは文化としてつなげたいんです。」(溝口さん)と、薪割りや薪サウナの体験も“ここにある資源を活かす”という考えにつながっている。
地元の木材や職人技を活かした宿泊棟は、奥多摩の自然に溶け込み、静寂と星空、川のせせらぎを背景に、非日常でありながらも「暮らすように泊まる」感覚を目指している。食事は、自家農園や地元農家、川漁師などから届く旬の食材を使って、シェフが土地ならではの旬を提供。森と川を最大限に活用した、奥多摩ならではの五感を使ったアクティビティも体験できる。
このSatologueでの滞在・体験は、青梅線のほかの駅にも展開が可能だ。沿線全体に訪問者を均一化させることができれば、地域の負担を減らしながら広域的に経済効果を波及させられる。沿線全体で「観光を支える人材」が育ち、地域間で知見が共有され、13駅に広がる「沿線まるごとホテル」全体の価値向上につながり、持続可能性が高められるだろう。
Satologueによって、大きな一歩を踏み出した沿線まるごとホテル。地域資源を活用して、地域住民と共に立ち上げる持続可能な新たな地方創生の1つの手法として期待がかかる。

山を分け入り、涼しげなわさび田へ向かう

わさび田ツアーをガイドしてくれたTOKYO WASABI、兄の角井仁さん(左)と弟の角井竜也さん(右)

レストランスペース。宿泊時はこちらのスペースにて夕食をいただく。

宿泊棟。大きなアーチを描く天井の先には大自然が広がる。

Satologue(さとローグ)
所在地:東京都西多摩郡奥多摩町棚澤1 【地図】
アクセス:JR青梅線「古里駅」より徒歩約15分(※JR青梅線「鳩ノ巣駅」から送迎有り)
体験:記事内で紹介したわさび田ツアーなどの体験は、さとローグへ問い合わせ。
予約方法:公式サイトの予約フォームより
URL:https://satologue.com/
SNS:Instagram https://www.instagram.com/satologue/


サステナブル・トラベラー|Chiara Terzuolo(キアラ・テルツオロ)
『The Vegan Guide to Tokyo』『Hidden Japan』著者。日本で10年以上、文化・観光分野での執筆やプロモーションに携わる。『The Japan Times』『Japan Today』『Lonely Planet』などで記事を執筆し、JNTO、東京都、⾼知県など公的機関の案件にも参加。NHK「ニュースで日本語を学ぼう」では共同アンカーも務めた。都市型オーガニック菜園やプラントベースのライフスタイルなど、サステナブルな暮らしを実践中。
※本内容は、「公益財団法人 東京観光財団 環境配慮型旅行推進事業助成金」を活用して実施しています。
文/All About Japan編集部 写真/湯浅立志