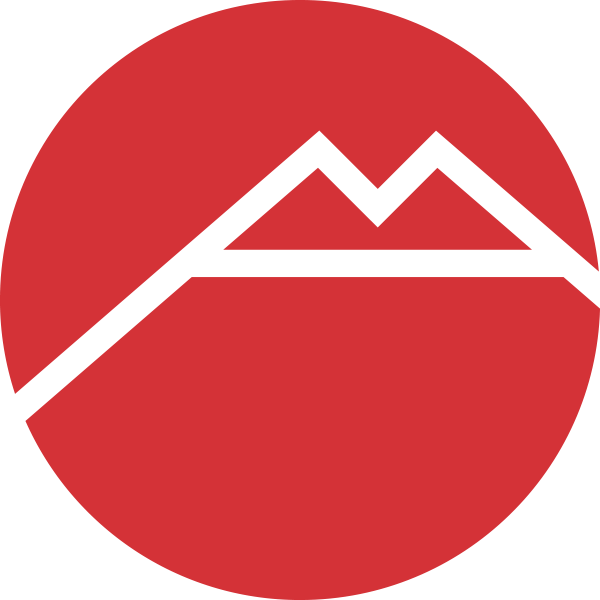日本の国立公園を、グローバルな観光資源に/佐々木真二郎(環境省 自然環境局 国立公園課 国立公園利用推進室 室長)×江幡哲也(株式会社オールアバウト・代表取締役社長)

環境省 佐々木室長(左)、オールアバウト 江幡代表取締役社長(右)
日本の国立公園は、アメリカ等の国立公園とは異なり、公園内に多くの私有地が含まれている。国立公園内に住んでいる人も多く、農林水産業や観光業なども行われていることから、公園の成り立ちを含めた「独自のストーリー」を大切にしてきた。
また近年では「保護」だけでなく「利活用」のための取り組みにも注力している。利活用をさらに進めることで、インバウンドを含めた観光誘客に寄与するだけでなく、昨今問題になっているオーバーツーリズム対策にもつながる。
今回は、国立公園の利用促進を担う環境省 国立公園課 国立公園利用推進室 佐々木室長と、海外も視野に入れたデジタルメディアのパイオニアであるオールアバウトの江幡社長が、「国立公園と観光」のいま、そして未来について語り合う。
国立公園を「世界水準のナショナルパーク」としてブランド化

釧路湿原国立公園(北海道)は、日本最大の釧路湿原と、そこを流れる釧路川とその支流、そして湿原を取り囲む丘陵地からなる。

江幡社長(以下:江幡) 本日はよろしくお願いいたします。最初に、簡単に自己紹介をお願いできますか?
佐々木室長(以下:佐々木) 私は2002年に技術職として環境省に入省し、国立公園の管理や、希少な野生生物の保護、エコツーリズムなど、主に自然環境に関する仕事に携わってきました。また、東日本大震災後には、自然環境を生かした復興ビジョンづくりや、「みちのく潮風トレイル」という東北太平洋沿岸を一本の道でつなぐ、約1,000㎞のロングトレイルを設定する仕事にも関わっています。現職に就く前は、福井県庁に出向して、コウノトリの野生復帰や、特徴的な縞模様の地層をテーマにした「福井県年縞(ねんこう)博物館」の建設にも携わりました。

江幡 ありがとうございます。自然保護から復興支援まで、本当にさまざまな業務を手掛けてこられたのですね。
本日は国立公園を主なテーマにお話をうかがいたいと思っています。まず国立公園の利活用についてですが、現在はどのように利活用されていて、どんな課題があるのでしょうか?
佐々木 現在、日本には自然公園法に基づいて国が指定した国立公園が35あり、指定目的は日本を代表する風景地の「保護」と「利用」です。しかし、各地で開発が進んだ高度成長期など、環境省では長い間保護に軸足があり、利用促進の取り組みはどちらかというと十分ではありませんでした。1931年に国立公園制度ができた当時はたいへん盛り上がって、全国各地で「うちも国立公園に指定してほしい」という声が数多くあったのですが、その後、求心力が失われる時代が長く続きました。さらに、世界遺産が広く知られるようになると、しだいに国立公園の注目度が下がっていってしまったのです。特にインバウンドに対しては、国立公園のポテンシャルを十分に発揮できていないという課題がありました。
江幡 そうした課題に対して、どのような対策を行ってこられたのでしょうか?
佐々木 政府は2016年に訪日外国人をさらに呼び込むことを狙った「明日の日本を支える観光ビジョン」を策定しました。これにひもづいたプロジェクトの一つとして、環境省では、日本の国立公園を世界水準のナショナルパークとしてブランド化することを目的に、「国立公園満喫プロジェクト」という取り組みをスタートさせました。
国立公園満喫プロジェクトでは、国立公園を訪日外国人にとって魅力のある場所とするべく、ソフト・ハード両面で、約10年にわたってさまざまな取り組みを行ってきました。その成果が、近年功を奏していることを感じます。例えば、従来は「温泉に入りたいから箱根に行こう」という人はいましたが、「国立公園の箱根に行こう」という人はいませんでした。しかし最近では「国立公園だから行ってみよう」とか、「今度は別の国立公園に行ってみたい」という形で、国立公園が「旅の目的地」になりつつあるのです。国立公園を訪れる訪日外国人も増加傾向にあって、利活用は着実に進んできていると感じています。

阿蘇くじゅう国立公園(熊本県・大分県)では、大自然の中での乗馬体験が楽しめる。
江幡 私は久住高原が大好きで、阿蘇くじゅう国立公園をたびたび訪れているのですが、実に魅力的な観光資源だと思います。まさに環境と観光のエコシステムをつくっているということですよね。
佐々木 ただ、「世界水準のナショナルパークとしてのブランド化」という点では、まだ途上にあると感じています。これまでの観光は「量」を求める観光でしたが、今は「質」や「満足度」を求める時代へと変わってきています。滞在型・高付加価値観光で顧客満足度を高め、その結果として地域に落ちるお金が増え、地域経済が活性化していく。来訪者が自然環境の保全活動に参加したり、保全のための経費を寄付したり、さらには地域課題解決に参画するなど、「保護と利用の好循環」を作っていかなくてはなりません。
江幡 観光の質や満足度を高めるために、どんな取り組みを行っているのでしょうか?
佐々木 まずは、地域ぐるみで「国立公園の魅力や価値について共通認識を持つ」ことが重要だと考えました。日本の国立公園は、宿や土産物屋、ガイドなど地域の方々や民間企業など、多くの関係者と協働しています。国立公園の運営や情報発信にあたっては、環境省だけでなく、多くの関係者とともに実施することが不可欠なのですが、発信する側の関係者が、国立公園に対してそれぞれ異なるイメージを持っていたのでは、伝えるべき魅力が曖昧になり、「ブランド」として認知されにくくなってしまいます。
一方で、日本の国立公園は古くから人が住み、自然と共生する暮らし・文化が、地域ごとに特色を持ちながら営まれてきました。そこで、地域の自然と、暮らしや文化が織り成すストーリー※をみんなで紡ぎ、それを共有することで、国立公園に関わる人たちが、その魅力を自分の言葉で語れるようにする「インタープリテーション計画」の作成を進めています。こうした活動を通じて、来訪者の方々に、感動的な自然の風景だけでなく、その風景によって育まれた自然と共生する暮らしや文化との関係を感じていただき、より質の高い、満足度の高い経験を提供できるようになることを目指しています。
※例:阿蘇くじゅう国立公園のストーリー

西海国立公園(長崎県)は、リアス海岸と200余りの島からなる九十九島を含め、大小400に及ぶ島々が繰り広げる外洋性多島海景観が特徴。
日本の国立公園は「自然共生の教科書」

国立公園に関わる人々のストーリーを「聞き書き」し、冊子とWebページにまとめる『国立公園ものがたり』。写真は、雲仙天草国立公園(長崎県・熊本県)での、「奥雲仙の自然を守る会」代表、中田妙子氏へのインタビューの模様。
江幡 そんな国立公園ももうすぐ100年を迎えるのですよね? 現在、「国立公園100周年」に向けた記念事業が進んでいるとうかがいました。
佐々木 1931年に自然公園法の前身である国立公園法が制定されてから、2031年で100周年を迎えます。そこで、国立公園の自然を舞台に連綿と続いてきた歴史・文化・暮らしについて、地元の方々に語っていただく『国立公園ものがたり』という冊子とWebページを制作し、多言語で発信していきます。
特徴的なのは、一般的なインタビューとは異なり、「聞き書き」のスタイルで制作する点、そして、情報を届ける対象者が「国立公園で暮らす人たち」である点です。国立公園に関わる人たちは、どんな自然観を持っているのか、そしてどのような思いを抱きながら暮らしているのか、…かれらの人生について話してもらい、それを話し言葉で文章化するのです。
江幡 なぜ「聞き書き」で、「国立公園で暮らす人たち」に向けた発信をするのでしょうか?
佐々木 その土地に暮らす人々の自然観、生きざまは、読み手の共感を呼ぶんですよ。これまで環境省では、地形、生物の生態といった科学的な言葉で、国立公園の魅力を語ることが多かったのですが、その地域の良さ、自然と暮らすことの素晴らしさなどは、それだけでは伝わりにくい。やはり実際に暮らしている人たちの「生の声」を聞くことで、深い共感が得られると思うのです。
日本の国立公園は、アメリカ等の国立公園とは異なり、公園内に多くの私有地が含まれています。豊かな自然の中に、土地に根ざした生活文化があり、自然と共生するための知恵が育まれてきた、いわば「自然共生の教科書」ともいうべき場なのです。ただ、そうした文化や知恵は、時代とともに失われつつあります。それを再び取り戻すためには、人々の思いを紡ぎ直さなければいけません。
それを聞き書きで「見える化」し、地域のみんなで共有することを通じて、「この地域での暮らしは、大変なことも多いけれど、良いこともいっぱいあるよね」という捉え直しをしてほしいと思っています。地域の未来が共有できれば、「何か楽しいことをやろうよ」という盛り上がりが生まれ、新たな地域を元気にするプロジェクトがどんどん生まれてくる。こうしたネットワークを広げていく上で、聞き書きのストーリーはとても価値があると私は思っています。
江幡 お話をうかがっていると、私までワクワクしてきます。国立公園の利活用がさらに進むことによって、近年、課題になっているオーバーツーリズムの解決にもつながりそうですね。
佐々木 大きく貢献できると思っています。日本全国に35の国立公園があり、それぞれの土地に“オンリーワン”がありますから、多くの方に足を運んで楽しんでもらえれば分散も進んで、日本全国が元気になります。それこそが国立公園の果たすべき役割かなと思っています。
江幡 本日はありがとうございました。

【Profile】
佐々木真二郎(ささき しんじろう)環境省 自然環境局 国立公園課 国立公園利用推進室 室長
2002年、環境省に入省。環境省レンジャーとして、国立公園や世界自然遺産の保全管理、希少野生生物の保護を担当。東日本大震災では、自然環境を活かして復興に貢献する「グリーン復興プロジェクト」として、みちのく潮風トレイルの整備などにかかわる。現場では、阿蘇くじゅう国立公園の管理や、長崎県対馬のツシマヤマネコの保護増殖事業を担当。また、2017年から2019年まで福井県自然環境課長として、年縞(ねんこう)博物館の建設、コウノトリの野生復帰事業や自然再生事業を担当。2024年7月より現職。
江幡哲也(えばた・てつや)代表取締役社長兼グループCEO
1987年株式会社リクルート入社。エンジニアとしてキャリアをスタートし、その後数多くの事業を立ち上げる。1996年に立ち上げたキーマンズネットにおいては、14個のネット関連特許を取得し、高い評価を得る。1998年度全国優秀システム賞受賞。2000年、株式会社リクルート・アバウトドットコム・ジャパンを設立。代表取締役社長兼CEOに就任。2004年、株式会社オールアバウトに社名を変更。2005年9月にJASDAQ上場を遂げる。専門家ネットワークを基盤に世の中の「情報流・商流・製造流」の不条理・不合理に対してイノベーションを起こし、“個人を豊かに、社会を元気に”することを目指す。2022年度 東京都市大学大学院 総合理工学研究科客員教授に就任。